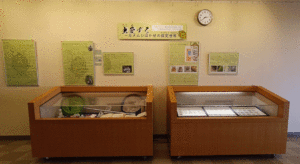横須賀市自然・人文博物館の調査研究活動や資料整理活動、教育普及活動への協力活動を紹介します
基礎昆(基礎から学ぼう昆虫学)2025年度第Ⅳ回授業
・2025年8月日:
最終回は午前中は博物館周辺でセミの抜け殻探し、午後は抜け殻集計と基礎昆の振り返り。今年は昨年に比べて抜け殻は少なかったようです。

今年も参加者の皆様、スタッフの皆様お疲れ様でした。
基礎昆(基礎から学ぼう昆虫学)2025年度第Ⅲ回授業
・2025年7月13日:
3回目は観音崎公園での虫探し。朝は曇りでしたがかなり暑くなったようです。集計によると160種の昆虫が確認できたようです。
基礎昆(基礎から学ぼう昆虫学)2025年度第Ⅱ回授業
・2025年6月15日:
基礎昆の第二回が開催されました。昨日からの悪天で風雨が強まる中の開催となりましたがほぼ「全員が出席!」し無事開催されました。今回は予定を変更し午前中に標本の作り方のレクチャーをした後は、2グループに分かれ展翅の実践と展脚の実演。展翅は1~2頭の展翅を行い、皆さんの展翅の出来栄えは優れたものばかりだったとの事。(展翅板を短くして、作業性、収納性を上げたのも功を奏したか?)午前中の終わりには風雨も止み日が射す天気に。
お昼休み後半には大熊会員が用意した「繭から絹糸を採る」の実演が有り、小学校などでカイコを飼育した事のある皆さまから色々は話を聞けたとの事。午後は2グループに分かれて平和公園へ生き虫探し。午前の悪天から網を持ってこなかった参加者も居られたようで悔しい表情を浮かべていたとの事。
基礎昆(基礎から学ぼう昆虫学)2025年度第Ⅰ回授業
・2025年5月25日:
本会が毎年協力させて頂いている基礎昆の第一回が開催されました。今回はHP執筆子も講師の一人として参加し、皆様と自己紹介を兼ねて話す事が出来たり、平和中央公園を歩いたりする事が出来ました。最後は飼育材料を皆さんに配布し1回目は終了いたしました。
標本調査@横須賀自然・人文博物館
・2025年2月15日:
会員の有志が集まり横須賀自然・人文博物館に所蔵されている標本の調査を実施した。第一目標は三浦半島産ネブトクワガタで「三浦半島に住む昆虫からのメッセージ」に掲載された標本である。バックヤードと言う普段はお目にかかれないエリアに入り所蔵された色々な標本を見ながら目標の虫を探しました。
捜索を始めて約1時間の11時11分ネブトクワガタがその姿を現した!ラベルには約70年前の1954.6.24 KUGO Yokosukaと記載されている。ラベルが付けられ収蔵された標本は時を超え、この時、この場所にこの虫が居た資料として脈々と受け継がれて行くのである。大成果に記念写真を一枚。
お昼を挟んで午後さらなる発見が!
なんとアカアシクワガタも発見する事が出来た!ラベルは1986.8.18横須賀市鷹取山約40年前である。更にコブスジコガネの仲間の標本など貴重な標本を見つける事が出来た。この日集まった有志の皆様お疲れ様でした。
2024年度スタディトーク自然の探究①:三浦半島の昆虫研究発表会
・2024年11月23日:
三昆研メンバーが思い思いの内容を発表されました。 ①内舩俊樹学芸員「平和公園の昆虫」…隣接する平和公園が整備されたのを機に、生息する昆虫・植物の状況を調査している。博物館ホームページに詳細報告。
②長崎仁平 三昆研会員「ナナフシの研究」…基礎昆で課題のナナフシモドキを飼育し、
疑問が生じたことを納得するため、飼育方法を工夫し、与える葉の種類を試し、
大きさの基準を身長から体重に着目等々の発表であった。
③後藤 渚 三昆研会員「僕とタガメが出会うまで」同じく基礎昆参加から三昆研会員となった小学4年生。
かつて各地の水辺で見られたが、今は絶滅危惧種であり容易には見つからない。
このタガメを求めて福島県方面の水田地帯を探索。
栃木県でその努力が実り幼虫発見飼育。
その後成虫発見まで行き着きさらに生息環境まで言及される内容であった。
④髙橋颯汰郎 三昆研会員今中2になった演者が、小1の時セミの羽化に疑問を持ち、観察・研究を進めている、
その経過報告でもある充実した内容の説明であった。
⑤大熊宏明会員「三浦半島に侵入してきた昆虫種」三浦半島の位置・地形から昆虫が外から入り難く出にくい。
人が持ち込んだ。温暖化と荷物に付いて入った。事を前提に過去・現在・未来の昆虫名をあげて説明された。
内容がカメムシ・甲虫・ハムシだったので、「チョウなど他には?」との質問が出た。
発表時間の制限もあり候補種を1/3に減さざるを得なかったとのこと。
⑥小口岳史会員「2023年三浦半島のシロチョウ科チョウ類」半島のチョウ類のデータ収集をされている中で、
2023年のショロチョウ類の調査結果を基に説明され、
秋にモンシロチョウが減少した原因の推測を、2024年春の調査結果も比較し、説明された。
基礎昆(基礎から学ぼう昆虫学)2024年度第Ⅳ(最終)回授業
・2024年8月18日:
本会が毎年協力させて頂いている基礎昆の第4回が開催されました。今回は最終回と言う事で博物館にて総括、セミの抜け殻探し&セミの抜け殻調べでした。午前中参加者の皆さんは炎天下のなか博物館周辺でセミの抜け殻をエリア毎に探しました。
午後は各エリアで見つけた抜け殻を、区別点を見ながら種類ごとに分けて集計し約200個近い抜け殻を見つけることが出来ました。
総括ではグループに分かれて思い出に残った虫、感想などを思い思いに語って頂き、虫だけでなく人との触れ合いも有り人間的に成長した、また来年も・・・など色々な思いを聞くことができ良かったです。最後は修了証授与で終了でした。
今回は講師側に色々な方が関わって頂き、三昆研の虫屋虫屋した雰囲気だけでなく馴染みやすい雰囲気だったのでは?と思います。今後もそう言った利点を生かしたイベント協力が出来ればと思いました。
基礎昆(基礎から学ぼう昆虫学)2024年度第Ⅲ回授業
・2024年7月14日:
本会が毎年協力させて頂いている基礎昆の第三回が開催されました。今回は観音崎公園での虫探しです。朝待ち合わせの「森のロッヂ」に向かう途中も参加者たちがネットを持ち散策する姿が見られ始まる前から気合を感じられました。まずは皆さんの近況報告を聞きましたが、自分が子供の頃そこまで考えていたかなぁ?と思わされるくらい色々考えて虫と向き合っているんだなァと思わされました。
講師の太田会員からはこの場所の良い虫、狙って欲しい虫を教えて頂き午前中は近場を散策。前日の予報では午前中雨との事でしたが、小雨が一瞬ぱらつきましたが天気は持ってくれました。お昼前に各講師から気にしてみて欲しい虫の話などを頂き昼食。そんな中でも元気に網を持って走り回る参加者の姿も有りました。
午後は午前中と変わって強い日差しで夏の虫を追うにはもってこいの天候でした。各自がネットを持って好きな虫を追いかけまわり、まさに昆虫採集の原点の様な風景でした。今回は約150種の昆虫を確認する事が出来、かなりの成果を上げることが出来たのでは?と思っています。
一方で各自が好きな虫を追いかけられたのは良かったのですが、若干纏まりが無かったのでは?先行している人達と後ろを行く人たちの見れた虫のバランスはどうだったのだろうか?など講師・運営としては課題が残る講座となりました。
基礎昆(基礎から学ぼう昆虫学)2024年度第Ⅱ回授業
・2024年6月9日:
本会が毎年協力させて頂いている基礎昆の第二回が回が開催されました。今回は2回目と言う事で、前回の飼育の近況、最近見つけた虫の話をグループごとに発表しました。その後お昼までは2班に分かれ平和中央公園で虫探し。初となるモンキチョウやムラサキシジミなどを採集する事が出来ました。午後は昆虫標本の作り方講座を実施したのですが、各々が自由に出来た半面、講師側としては課題が残る講座となりました。
基礎昆(基礎から学ぼう昆虫学)2024年度第Ⅰ回授業
・2024年5月26日:
本会が毎年協力させて頂いている基礎昆の第一回が開催されました。今年も大盛況の始まりとなりました。本イベントを通じて新たな発見や、三昆研の会員と若い虫好き達との世代を超えた交流を通じて虫に更にのめり込む一歩となればいいですね。
展示前協力・資料整理協力
・2024年4月14日~2024年5月25日:
本会会員で惜しくも今年の2月に逝去された故鈴木裕さんのカメムシ研究の一部を展示する「虫愛ずる-カメムシはかせの探求世界-」の展示を開始しました。展示前のお手伝い、膨大な数のガガンボの標本整理をお手伝いさせて頂いております。
本展示は横須賀自然・人文博物館の3階にて開催中です。各種カメムシの標本、採集用具や野帳だけではなく、鈴木裕さんの生涯・人柄に関しても触れられ素晴らしい展示です。
資料整理協力
・2012年6月23日:
7月14日から始まる「三浦半島のチョウ」展の準備を兼ねて、博物館に収蔵されているチョウ類の標本を整理しました。
教育普及協力
・2012年8月26日:
5月27日から全4回の日程で開催された博物館主催「基礎から学ぼう昆虫学(基礎昆)」が本日無事に最終日を迎えました。残暑厳しい晴天となった最終日には参加者20人と講師役の当会会員8名が集まり、各自の成果発表はパワーポイントや大きな模造紙での発表など充実しました。続く宮川つぐみさんと宮川翼さんによる「昆虫おもしろ話」では、「2人で12年間も続けた城ケ島のセミ調査」と題した興味深いお話がありました。最後に恒例のセミのぬけ殻さがしを行い、たった30分で553個ものぬけ殻が集まり、全員で種を調べたところ、アブラゼミ420個、ミンミンゼミ123個、ツクツクボウシ6個、ニイニイゼミ4個という結果になりました。最後に参加者全員に「修了証」が渡され、2012年度の基礎昆が終了しました。
全4回の参加者は延べ88名。講師は当会会員が延べ24名であたりました。
・2012年7月14日:
企画展示「三浦半島のチョウ」展が開催されました。今日からは3連休限定の「生きているチョウ」の展示も行います。三浦半島で採集したカラスアゲハ、モンキアゲハ、ジャコウアゲハなどを、幼虫やサナギとともに展示しました。7月14日は初日ということで、午後に学芸員と一緒に展示解説を行いました。
展示解説していると、サナギに変化が・・・なんと、カラスアゲハの羽化が始まったのです! ふつうは夜~明け方に多いチョウの羽化ですが、大勢のギャラリーの前で、しかも解説している会員の手にとまって翅を伸ばしていました。
展示初日を飾る印象的な出来事に、展示解説は一層盛りあがりました。
※展示は2012年9月30日に終了しました。